ゴールデンウィークの夜空を飾る「みずがめ座η (エータ)流星群」。ハレー彗星由来の微細ダストが大気を駆け抜け、毎年5月上旬には夜明け前の空を流星が彩ります。
2025年は5月5日(月)深夜~6日(火)明け方にかけてピークを迎え、月明かりの影響も少なめ。1時間あたり5~10個の流星が期待できる絶好のチャンスです。本記事では、ピーク予想や観測スポット、撮影テクニックを徹底ガイドします。
みずがめ座η流星群とは?
ハレー彗星が残したダスト(微小な塵)が地球の大気に飛び込み、光の筋となって見えるのがみずがめ座η(エータ)流星群です。南半球では年間でもトップクラスの出現数を誇りますが、日本など北半球でもゴールデンウィーク終盤の“夜明け前ショー”として人気があります。流星は秒速約65 kmという高速で飛び、残光が数秒続くのが特徴です。
2025年はいつ・どこで見える?
| 観測項目 | 2025年のデータ | チェックポイント |
|---|---|---|
| 極大(ピーク) | 5月6日(火) 3:00〜4:30 JST(中心時刻は4:30 JST)Astronomy Magazine | 放射点が十分に高く、月も沈んでいる時間帯 |
| 月齢・月明かり | 5月4日に上弦→ピーク前後は月が午前2時半頃に沈むAstronomy Magazineタイムアンドデート | 月明かりの影響はほぼなし |
| 見頃期間 | 5月3〜9日(最盛期は5〜7日未明)国立天文台 | 晴れた日を狙って連夜チャレンジ |
| 出現数(日本) | 暗い空で 5〜10個/時(条件良い南半球は50個超/時)国立天文台Time | 高度が低い分、流星は長い軌跡で出現 |
ベストタイム:5月6日未明 2:30〜明け方(関東以西は4:30ごろまで)。ゴールデンウィーク最終盤なので、深夜ドライブ → 郊外の暗い空で夜明け待ち、が王道です。
観測のポイント 5か条
防寒 & 休憩
5月でも山間部は5 ℃前後。防寒着と温かい飲み物を準備し、眠気対策に仮眠を。
放射点は南東の低空
みずがめ座ηは夜半過ぎに昇り始め、夜明け直前で高度30°程度。空全体を見渡す姿勢(レジャーシートで仰向け or リクライニングチェア)が◎。
月明かりを背中側に
ピーク前後は月が沈むが、残光が気になる地域は背を向ければ視認性UP。
光害・湿度対策
東京近郊なら奥多摩、千葉県銚子周辺など、地平線まで暗い場所が理想。
目を暗闇に慣らす
スマホはナイトモード+最低輝度、観測開始15分前から光を避けると流星の細い光も見える。
流星撮影プリセット(どんなカメラでも応用可)
| 設定項目 | 推奨値 | 解説 |
|---|---|---|
| レンズ | 広角(フルサイズ換算で14~24mm相当) | 流星の長い軌跡を画角に収めやすく、星空全体を写し込める画角を選ぶ |
| 絞り(F値) | 最小F値(お使いのレンズの開放) | 入射光を最大化してシャッタースピードとISOを抑え、ノイズを減らす |
| シャッター速度 | 5〜15秒 | 短すぎると流星の軌跡が切れる、長すぎると星が線状に流れすぎるのでバランス重視 |
| ISO感度 | 800〜3200 | カメラの高感度耐性や月明かりの有無に合わせて調整。暗い空なら高め、光害が強いなら低めに設定 |
| フォーカス | マニュアル∞(ライブビュー拡大で微調整) | スポットライトや月で明るい星に合わせ、ピーキング機能や拡大で無限遠を正確に合わせる |
| 撮影モード | バルブ(B)または連写+インターバル撮影 | ● バルブでバルブ開放→固定時間後に手動またはリモートでクローズ ● インターバルタイマー機能で連続撮影し、後処理で比較明合成 |
活用ポイント
- 比較明合成:RAW連写を合成して一枚の“流星群写真”に。Lightroomや専用ソフトでノイズリダクションとトーン調整を同時に行うと◎。
- インターバル設定:撮影間隔はシャッター速度+1秒程度空けるのが目安。バッファフル時の待ち時間も考慮しておく。
- バッテリー対策:長時間連写はバッテリーを消耗しやすいので、予備バッテリーか外部電源を準備。
- 天候&場所:流星観測は晴天が絶対条件。標高の高い山間部や海沿いの暗い場所を狙うと、より明るい流星や淡い流星痕が見えやすくなります。
これらの設定をベースに、お使いのカメラ固有の性能(高感度ノイズ処理やインターバル機能の有無)に合わせて微調整すれば、どんな機種でもみずがめ座η流星群の撮影チャンスを最大限に活かせます。
まとめ
2025年のゴールデンウィーク最終盤は、月明かりに邪魔されない絶好のみずがめ座η流星群観測チャンス。
- ピーク:5月6日未明
- 見頃:夜明け2時間前ごろから
- 出現数:1時間に5〜10個を期待
ぜひカメラを携えて早起きし、春の夜明け前にハレー彗星の置き土産を受け取りましょう!
観測スポットや装備の質問はコメント欄からどうぞ。
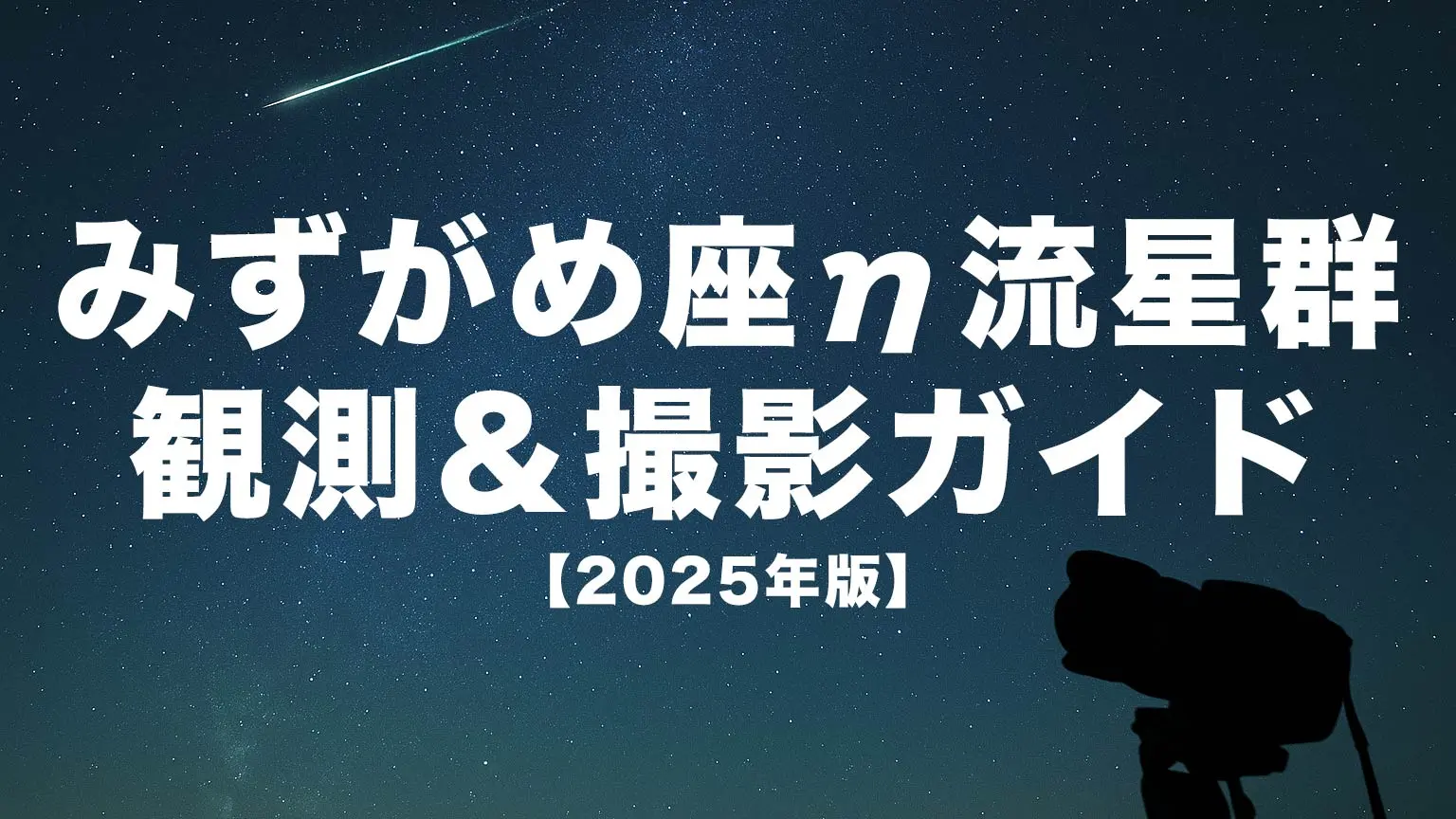
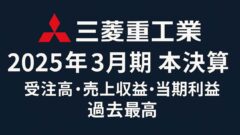
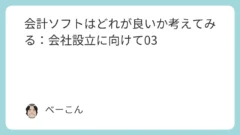
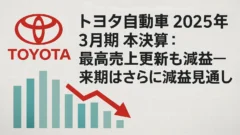
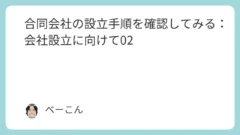
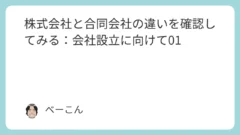
関連記事